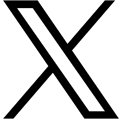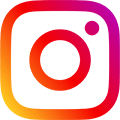教員紹介
食料資源学科 食料生産環境コース
藤田 一輝 助教
FUJITA Kazuki
専門分野:
土壌肥料学
- キーワード:
- 土壌微生物
- 土壌肥沃度
- 微生物バイオマス
- 土壌酵素
研究内容
作物生産において肥料は不可欠であり、作物生産性の向上に大きく貢献しています。しかし、肥料の原料となる鉱石や化石燃料などは特定の地域に偏在しており、資源の少なく肥料原料のほぼ全量を輸入に依存している日本などは資源争奪や価格高騰の影響を強く受けます。また、土壌に施用された肥料成分の多くは作物に吸収されることなく、土壌に蓄積し、その一部が河川や海洋などの環境中に溶脱し、富栄養化などの環境汚染を引き起こす原因となっています。
当研究室では、土壌微生物のもつ機能を活用し、土壌に蓄積した養分の再活用や肥料の利用効率向上による環境負荷を低減した食料生産を目指した研究を行っています。
● 微生物の酵素生産に寄与する要因の解明
土壌中の養分の多くは有機物として存在し、植物が直接吸収することのできない形態となっています。微生物には、それらの有機物を分解し、養分を植物の吸収可能な形態に変化させる働きがあります。その際に、微生物は酵素を土壌中に分泌することで、有機物の分解を行っています。微生物の分泌する酵素の量によって有機物の分解速度も変化します。微生物が分泌する酵素の量を制御することが可能となれば、土壌に蓄積した有機物から植物に供給される養分量もコントロールできると考えられます。現在では、微生物の酵素分泌に寄与する環境要因について研究を行っています。
● 微生物バイオマスによる養分供給能の評価
植物の成長に必要な養分のなかでも特に、リンは土壌を構成する鉱物と結合することで植物が吸収できない形態へと変化します。土壌と結合したリンは植物や微生物の機能によっても利用されにくく、日本に広く分布する黒ボク土は特にリンと結合しやすいため、肥料として土壌に施用されたリンの90%以上が土壌に蓄積しています。微生物に取り込まれた養分(微生物バイオマス)は土壌と結合することを防ぐとともに、微生物の死滅後、他の有機物よりも分解されやすいため、植物への養分供給源の1つと考えられています。現在では、微生物バイオマスの制御要因や植物の養分吸収との関係について研究を行っています。

 交通のご案内
交通のご案内 お問い合わせ
お問い合わせ よくあるご質問
よくあるご質問 ENGLISH
ENGLISH