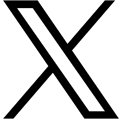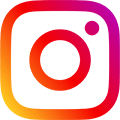農学生命科学研究科(修士課程)
農学生命科学研究科(修士課程)
学部教育との連携を重視し、より高度な学際的かつ国際的な教育研究を行い、熟練した地域社会の発展に貢献できる高度専門技術者や国際的視野をもつ優れた技術者、時代の要請を先取りして先端的研究に挑戦できる研究者となりうる人材の養成を目的とします。
修業年限は原則として2年ですが、学部からの飛び級制度も設けています。修了者には修士の学位が授与されます。また、ティーチングアシスタントという制度があり、報酬を得て学生が教員の教育活動や実験の補助を行うこともできます。
①1専攻5コースの設置
- 学部学科に対応する「生物学」、「分子生命科学」、「食料資源学」、「国際園芸農学」及び「地域環境工学」の5コースを設置し、進学する学生にとって専門分野の選択が容易なものとする。
②専門教育研究プログラムの設置
- 多様な進学希望に対応するために「学術研究プログラム(研究者養成)」と「実践研究プログラム(技術者養成)」を設置する。
- 学生が期待しているように、限られた単位数内で’より広く’専門科目を選択できるように専門科目の多くは1単位とする。
③コース横断的講義科目(クロス・コース科目)の設定
- いろいろな分野の分析技術法を修得したいとの希望に応えるために、「クロス・コース科目」を設定する。
- 「分析技術法」は講義と実習を体系的に組み合わせた総合型授業であり、理論と実際を教授する科目である。
④「副コース科目」の設定
・自コース科目に隣接する領域を埋める他コース専門科目
・専門分野に関連する他研究科開講科目(指導教員と授業担当教員の承諾を得ること。)
⑤4学期制と1単位科目の導入
- 幅広い専門教育を目指す教育体制を整備するために、一部の専門科目の履修形態を4学期制(クオーター制)とする(1学期4-5月,2学期6-7月,3学期10月-11月,4学期12-2月(冬季休業期間をはさむ。))。
- 多くの専門科目は単独でも選択可能な1単位科目とする(○○A,○○Bと表記)。ただし、選択科目の「□□Ⅰ」と「□□Ⅱ」の表記は積み上げ型科目を示し学習の連続性を重視したもので、「□□Ⅰ」からの履修を求める科目である。
⑥入学前学習システムの導入
- 修士課程教育の充実を図るために、大学院進学希望者に対し、入学前の学習システムを導入する。科目履修届出制により、学部4年次前期及び後期に大学院の講義15単位までの受講を認め、入学後に単位の認定を行う。
科目の説明
①専攻共通科目
ⅰ) 必修科目
-
- 「農学生命科学特論Ⅰ」
社会実装の視点や起業力及び複眼的視点の養成を目指す。全コース共通で、卒業後の出口となる企業や行政・研究機関を見学するほか、これらの機関から講師を招聘する。 - 「農学生命科学特論Ⅱ」
- 「農学生命科学特論Ⅰ」
社会実装の視点や起業力及び複眼的視点の養成を目指す。コースごとに、卒業後の出口となる企業や行政・研究機関を見学するほか、これらの機関から講師を招聘する。
- 「プレゼンテーション演習Ⅰ・Ⅱ」
プレゼンテーションに関する留意点について学習した後に、スキルを養成するための演習を実施する。
ⅱ)選択必修科目
- 「学会等発表」(学術研究プログラム)
大学院生が自らの研究活動を通じて得たものを研究会や学会で発表(アウトプット化)するための手法を学習する(例:論文投稿の方法,学会発表の仕方,プラクティス・トークなど)。 - 「科学英語」(学術研究プログラム)
英語科学論文の論理的な論文構成、表現法、図表の作り方及びコツを学習する。 - 「実践研究推進セミナー」(実践研究プログラム)
先端研究の紹介を通して、また指導教員との意見交換を行いながら、修士課程に進学した学生の研究面のスタートアップを支援する。 - 「キャリア開発セミナー」(実践研究プログラム)
高度な専門技術者として社会貢献を目指す人材の育成を目的として、本学研究科修了生(OB・OG)を含む社会で活躍されている方々による講演や体験談を通して、学生の社会 - 職業的な自立に必要な能力や態度を涵養する。
ⅲ)選択科目
- 「分析技術法」
いろいろな分野の分析技術法を修得したいとの希望に応えるための講義と実習を組み合わせた統合型の授業。 - 「インターンシップ」
学生が一定期間企業等の中で研修生として働き、自分の将来に関連のある就業体験を行える授業。 - 「特別講義A」・「特別講義B」
学内外の講師による実務的な内容が多い講義。 - 「海外調査実習」
海外の生産現場や市場、研究機関の訪問調査を実施し、グローバルな視点を持ったイノベーション能力の向上を目指す。
②専門科目
各々のコースで開講する科目。
③副コース科目
・自コース科目に隣接する領域を埋める他コース専門科目
・専門分野に関連する他研究科開講科目(指導教員と授業担当教員の承諾を得ること。)
④弘大テーマ科目
「生命科学倫理学」、「白神の自然」
※試験に係る詳細については、「学生募集要項」をご覧下さい。
専攻,コース,分野,研究分野
| コース | 分野 | 専攻分野 |
|---|---|---|
| 生物学 | 基礎生物 | 分子細胞遺伝学、植物分子生理学、植物生理学、動物生理・分子進化学、発生・生殖生物学、植物細胞生物学、原生生物微生物学 |
| 生態環境 | 動物生態学、森林生態学、生物間相互作用学、植物分類学、進化生態学、環境生態学、動物分類学 | |
| 分子生命科学 | 生命科学 | 分子生物学、生化学・分子生物学、生化学・分子遺伝学、天然物化学、免疫生物学、動物生理学、細胞分子生物学 |
| 応用生命 | 天然物有機化学、環境微生物学、応用微生物学、生化学、植物生化学、微生物化学 | |
| 食料資源学 | 食料開発 | 作物育種学、作物ゲノム学、植物遺伝育種学、作物生理学、構成的微生物学 |
| 生産環境 | 昆虫生理学、植物病理学、土壌学 | |
| 国際園芸農学 | 園芸農学 | 果樹園芸学、家畜飼養学、家畜生理学、農業機械学、蔬菜園芸学、花卉園芸学、作物生態生理学、作物学、リサイクル工学 |
| 地域環境工学 | 農業土木・農山村環境 | 水利環境工学、水利施設工学、農地環境物理学、農地環境保全学、地域環境システム学、基盤造構学、地域環境利用学、地域環境計画学、山地環境保全学 |
※上記のコースに所属の上で、白神自然環境研究センター所属の教員の指導も受けることができます。
アドミッション・ポリシー
研究内容
生物学コース
| 分野 | 研究分野 | 研究内容 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 基礎生物 | 発生・生殖生物学 | 扁形動物プラナリアの生殖様式転換機構に関する発生・生殖生物学研究 | 小林一也 |
| 動物生理・分子進化学 | 脊索動物が持つ生理機能の進化に関する研究 | 西野敦雄 | |
| 原生生物微生物学 | 原生生物の細胞内共生の細胞生物学・進化学的研究 | 岩井草介 | |
| 植物分子生理学 | 植物分子生理学的手法を用いたラン色細菌や植物の基礎・応用的研究 | 大河 浩 | |
| 植物細胞生物学 | 植物の細胞分裂と細胞分化を制御する分子機構の研究 | 笹部美知子 | |
| 植物生理学 | 植物における葉緑体分化の制御機構の研究 | 藤井 祥 | |
| 生態環境 | 動物生態学 | 野生動物の行動・生態と生息場保全・再生技術 | 東 信行 |
| 水生動物の行動,生態,進化学的研究 | 曽我部篤 | ||
| 森林生態学 | 森林植物の生態と保全に関する研究 | 石田 清 | |
| 進化生態学 | 野生動物(主に小型無脊椎動物)の進化・生態学的研究 | 森井悠太 | |
| 植物分類学 | 植物の生活史とその進化,分類,保全に関する研究 | 山岸洋貴 | |
| 動物分類学 | 動物(とくに昆虫)の種多様性,系統関係,分布変遷の解明 | 相馬 純 | |
| 生物間相互作用学 | 植物や節足動物を中心とした群集における生物間相互作用およびその生態学的意義の解明 | 橋本洸哉 | |
| 環境生態学 | 農地における生態系保全や野生動物管理 | ムラノ千恵 |
分子生命科学コース
| 分野 | 研究分野 | 研究内容 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 生命科学 | 分子生物学 | ncRNAの構造と機能,生合成に関する研究,Functional RNomics | 牛田千里 |
| 細胞分子生物学 | オルガネラ形成における膜動態の解析,微生物感染によって誘導される細胞内ストレス応答の解析 | 森田英嗣 | |
| 生化学・分子遺伝学 | RNAを擬態するタンバク質の機能・構造解析,タンパク質合成異常回避システムの分子メカニズム | 栗田大輔 | |
| 天然物化学 | 植物や微生物の生理活性物質の発見とその農業への応用 | 高田 晃 | |
| 動物生理学 | 四足動物(とくに両生類)の四肢再生と皮膚再生,器官再生の分子機構の解明 | 横山 仁 | |
| 免疫生物学 | 癌の転移に関する研究,マウスの腫瘍細胞株の樹立,細胞運動の画像解析 | 畠山幸紀 | |
| 応用生命 | 環境微生物学 | 自然界に生息する微生物に関する研究 | 殿内暁夫 |
| 天然物有機化学 | 生理活性二次代謝物の探索・合成及びその利用法の開発 | 橋本 勝 | |
| 生化学 | ミトコンドリア電子伝達系の低酸素適応に関する研究 | 坂元君年 | |
| 応用微生物学 | 持続可能な化学品・エネルギー生産に向けた微生物機能の解祈と有用微生物の分子育種 | 園木和典 | |
| 植物生化学 | 植物や微生物における物質生産の機能解析と応用 | 濱田茂樹 | |
| 微生物化学 | 木質・草本系バイオマスの分解に関わる微生物の代謝機能解析 | 樋口雄大 |
食料資源学コース
| 分野 | 研究分野 | 研究内容 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 食料開発 | 作物育種学 | イネ遺伝資源・有用形質の遺伝解析と育種的利用に関する研究 | 石川隆二 |
| 構成的微生物学 | 複数の微生物で構成されるモデル生態系の構築と微生物間相互作用に関する研究 | 柏木明子 | |
| 植物遺伝育種学 | ウリ科作物において見出される有用形質の遺伝解析と育種への利用に関する研究 | 田中克典 | |
| 作物生理学 | イネ新品種を育成するための有用形質を支配する遺伝子の解析 | Dinh Thi Lam | |
| 生産環境 | 植物病理学 | 菌類の多様性と系統分類に関する研究 | 田中和明 |
| ウイルス・ウイロイドの病原性と宿主植物の防御応答に関する研究 | 直井 崇 | ||
| 土壌学 | 強酸性土壌における作物一土壌の相互作用に関する研究 | 松山信彦 | |
| 昆虫生理学 | 昆虫の発育・変態の分子レベルでの研究 | 金児 雄 | |
| 昆虫の内部及び外部環境応答遺伝子の研究 | 管原亮平 |
国際園芸農学コース
| 分野 | 研究分野 | 研究内容 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 園芸農学 | 果樹園芸学 | リンゴの単為結果に関わる遺伝子及び花芽形成遣伝子に関する研究 | 田中紀充 |
| バラ科果樹の果実品質評価及び野生種の育種的利用に関する研究 | 登島早紀 | ||
| 農業機械学 | 農産物の非破壊品質計測・情報技術の農業への応用に関する研究 | 張 樹槐 | |
| リモートセンシングの農業精密管理への応用に関する研究 農産物の品質計測・産地判別・鮮度評価技術などの開発研究 |
叶 旭君 | ||
| 蔬菜園芸学 | 蔬菜の発育生理,品質向上及び育種,組織培養に関する研究 | 前田智雄 | |
| 家畜生理学 | 初期成長期の栄養制御による家畜の生産能力の向上並びに新規飼料資源の機能性評価に関する研究 | 松崎正敏 | |
| 家畜飼養学 | ニワトリを中心とした動物の味覚受容機構の生理学的研究 | 川端二功 | |
| 作物生態生理学 | 作物の環境ストレスに対する耐性遺伝資源の探索とその耐性メカニズムに関する研究,植物による放射性セシウム吸収除去法の確立 | 姜 東鎮 | |
| 作物学 | 地球環境変動に対するイネなどの主要作物の応答に関する生理・生化学的研究 | 小早川紘樹 | |
| リサイクル工学 | 農林産廃棄物等のリサイクル技術に関する研究 | 廣瀬 孝 | |
| 花弁園芸学 | 花卉の繁殖・育種及び野生草本の利用や保護・保全 | 本多和茂 |
地域環境工学コース
| 分野 | 研究分野 | 研究内容 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 農業土木・農山村環境 | 農地環境物理学 | 積雪地域の普通畑と樹園地における窒素循環機構の解明 | 遠藤 明 |
| 地域環境計画学 | 環境と調和し活力ある農村空間を実現するための整備手法 | 藤﨑浩幸 | |
| 水利環境工学 | 国内外の農山村における水資源及び水環境に関する研究 | 丸居 篤 | |
| 基盤造構学 | 農業施設構造物の力学的安定と性能機能評価に関する研究 | 森 洋 | |
| 地域環境システム学 | 農地及び農業生産基盤を支える各種施設の情報利用と管理・運用 | 加藤 幸 | |
| 農地環境保全学 | 農地土壌をめぐる水・熱動態の解明・予測及び農地土壌の保全に関する研究 | 加藤千尋 | |
| 地域環境利用学 | 地中熱及び地下水を利用した農業に関する研究 | 森谷慈宙 | |
| 山地環境保全学 | 山地における土砂災害防止・流域環境保全や利用についての研究 | 鄒 青穎 | |
| 地域環境計画学 | 農村地域での集落機能維持や自然共生に関する社会科学研究 | 岸岡智也 | |
| 水利施設工学 | 水利施設の水理設計及び魚道の水理と淡水魚の挙動に関する研究 | 矢田谷健一 |

 交通のご案内
交通のご案内 お問い合わせ
お問い合わせ よくあるご質問
よくあるご質問 ENGLISH
ENGLISH