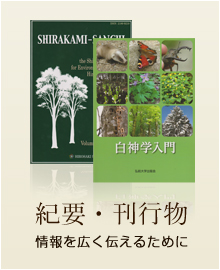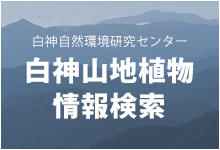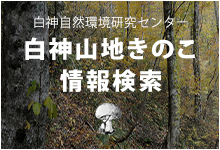センターの専任教員(相馬助教)が北日本の湿地に生息する昆虫に関する論文を出版しました!
書誌情報と解説を以下に示しました!
Souma, J. & Yamamoto, A. (2025) Taxonomic study of the subgenus Limnonabis of the genus Nabis (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae: Nabinae: Nabini) from Japan, with description of N. (L.) marihygrophilus sp. nov. inhabiting estuarine wetlands in northern Japan. Journal of Insect Biodiversity, 69 (1), 21–38. https://doi.org/10.12976/jib/2025.69.1.2
ナガマキバサシガメ亜属Limnonabis Kerzhner, 1968(カメムシ目:マキバサシガメ科:マキバサシガメ属Nabis Latreille, 1802)は全北区から6種が記録されています。日本に分布する3種(ハイイロナガマキバサシガメN. (L.) demissus (Kerzhner, 1968)、タイワンナガマキバサシガメN. (L.) sauteri (Poppius, 1915)、オオナガマキバサシガメN. (L.) ussuriensis (Kerzhner, 1962))は湿地でのみ得られ、それぞれ異なる草丈の単子葉草本群落にのみ生息します。本亜属は北日本から1未同定種が知られるものの、分類学的研究が長らく停滞していました。本研究では、この未同定種を新種シオナガマキバサシガメ N. (L.) marihygrophilus Souma & Yamamoto, 2025として記載しました。シオナガマキバサシガメは宮城県に位置する北上川の河口付近の湿地で20世紀末に採集されています。しかし、東日本大震災の津波が植生に被害を与えた後の2020年代に得られていません。よって、宮城県では姿を消した可能性があります。他方で、北海道に位置する勇払川の河口付近の湿地で2020年代に生息が確認されました。本亜属の採集には真夏の湿地で単子葉類をスイーピングする必要があり、熱中症の危険があります。高湿度かつ日陰がない場所で鋼鉄枠の網を全力で振り続けると、瞬く間に体力を消耗します。北海道では適度に休憩を挟めば夕方まで活動できましたが、宮城県では1時間が限度でした。活動しやすい季節に発生しないことを恨むばかりです…。

ハイイロナガマキバサシガメNabis (Limnonabis) demissus (Kerzhner, 1968)

シオナガマキバサシガメ Nabis (Limnonabis) marihygrophilus Souma & Yamamoto, 2025

タイワンナガマキバサシガメ Nabis (Limnonabis) sauteri (Poppius, 1915)

オオナガマキバサシガメ Nabis (Limnonabis) ussuriensis (Kerzhner, 1962)
本論文については弘前大学HPにプレスリリースが掲載されています。
PDF形式はこちらになります。
新種のシオナガマキバサシガメについての記事が北海道新聞(令和7年12月27日付)に掲載されました。
北日本で実施したフィールドワークの成果は今後も公表予定です!
既に投稿済みの原稿もあるので、出版が楽しみです!